
経営/マネジメント
まずはステークホルダーを分析、そこからステップアップ戦略を:ファンドレイジングの教科書 第1回
ファンドレイジングの教科書
▷ 1.まずはステークホルダーを分析、そこからステップアップ戦略を
▷ 2.そのつぎに、自団体の強みを認識するSWOT分析する
▷ 3.業界をみて他との区別できるか、ポジショニングを分析してみる
▷ 4.ステップアップ戦略をとるために、各階層にはどれぐらいの支援者が現在いるか
▷ 5.過去の寄付額はどれぐらいの金額かをドナーレンジチャートで
▷ 6.支援者のペルソナをしっかりと把握する、ヒアリング、その先のドナージャーニーも
▷ 7.支援者に応じた基本メッセージの発信する
▷ 8.ドナーレンジチャートから支援者が応援しやすい寄付メニューを構築する
▷ 9.広報ツールを棚卸して、支援者コミュニケーションの頻度も検討する
▷ 10.支援者拡大のためのツールを作成する
これまで当社のホームページにQ&Aがなかったので、実際に問い合わせ事例をもとにした回答例を多くの人々に役立ていただこうと「ソーシャルセクターのお悩み相談BOX」として20回にわたって連載してきたが、絶えずご相談いただくのは「自分たちでできるファンドレイジング」についてが多く、お悩み相談BOXでも回答例をお示ししているが、改めてページを割いてどのように進めていけばよいかについて解説していきたいと思う。
これらは私たちが、業務の一環として「ファンドレイジング戦略の策定へのサポート」へ入る際の実際のノウハウであり、公開することで広くお役立ていただきたいと今回の連載をスタートすることにした。
私にもできるファンドレイジング:ソーシャルセクターのお悩み相談BOX 第11話
わたしたちは何をしたらよいですか
団体の財源については自前で全て賄い自己完結していれば、悩みはないのだが、それだけでは課題解決が加速できない、多くの方々に知ってもらいたいという場合には、周囲の方々からの協力を得ることが必要となる。実はこれこそがソーシャルセクターで活動している意義と言っても過言ではない。
「どういうことか」と言えば、非営利で社会貢献団体を運営することは、社会課題の解決をすることが一番の目的に理解しがちだが、本当は、周囲に働きかけて多くの方々から共感を得て、参画を促す仕組みそのものが大切な役割。寄付やボランティアとして参加や、或いはポスターを観たり本や報告を読んだり、寄付はしなかったけれどもクラファンのプロジェクトページは読んだだけでも、これまで知らなかったことを知り、認識を新たにするというだけで「社会は変わる」からだ。
従って、社会貢献団体で実現したいことがある場合に、まず何をしたらよいかは「仲間を増やす」ことだ。一人では重い荷物も役割分担すれば、軽減することが出来るし、「寄付とかは無理だけどそれならば出来る」という方もきっと出てくる。実際に支えてくれている仲間は実は身近に居るのに当たり前すぎて感謝はおろか気づかないこともしばしばある。貴方たちの周囲に存在する大切な存在にまず発見するところから、始めていきたい。
ステークホルダー分析の進め方
団体の中の人、少しだけど協力者の方、などなどとワークショップをして、私たちの周囲に存在する人々を書き出してみよう。
【準備物】
模造紙、付箋紙、マジックペン
1)大きな模造紙の中心に円を描き、その周りにも大きさを変えて同心円を何本か描いておく。
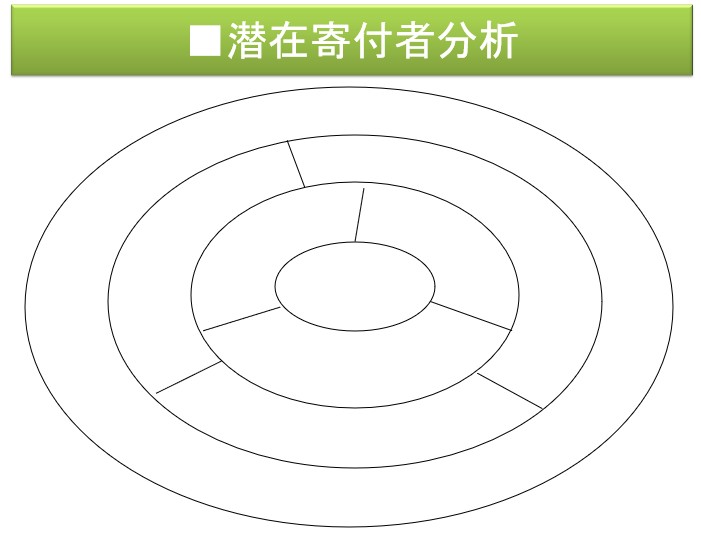
空白の円
2)円の中心に、団体の中で、それこそ中心になっている方々について書き出そう。
例:理事会、事務局、経営委員会 など
3)みんなで、周囲にはどんな方々がいるかを考えて書き出す。付箋紙を活用して1枚に一つ書き出すのだが、いきなり同心円へ貼り付けていくというよりは、まずそれぞれが誰とも相談せずに、自分で思い浮かんだものを書き出すのが良い。
これは集団の中で関係性の深い人からの意見に偏るというバイアスを避けるためである。ある程度の枚数がそれぞれの手元に溜まるまで少し時間をとって進めていく。例、少なくとも全体で30枚以上、または各自10枚程度 など
4)書き出した付箋を模造紙の円に張り付けていく。その際に、注意すべきことは、まず中心にいる方々との距離感。近い関係か、すこし遠い存在か、などを基準にして、位置決めをしていきます。
誰かが書いた付箋と同じようなものを自分も書いていれば、同心円のなかに出して、重ねたり、近くに位置しておきます。
5)少し全体を俯瞰して、同じような種類がゆるやかなグループとなるように、付箋の位置を点検していく。
6)参加者の手元にある付箋が全てなくなるまで、順番に紹介していく。
7)もう一度、全体を俯瞰して、グループどうしの位置関係なども微調整を行う。
8)付箋を張り付けて、グループを考えていくと、「こんな方もいる!」と新たな発見があるので、その際には新しい付箋に書き込み追加していく。
9)グループに着眼して俯瞰していくと、まだ存在していないグループなどに気づく場合もある。その場合には、思い切って、新しいグループに入る方々を書き出していく。
10)話し合って、みんなで納得できたら、その中で寄付の可能性が高いのはどこか、協力を得やすいのはどこかなどを具体的に想像していく。
この機会が、のちのち具体的にアプローチする際に大変役立ってくる。

ステークホルダー分析
ステークホルダー分析でわかること
- 団体の中心層に向かって、どのような関係性を持つ人々が存在しているかが明確になっていく。それらの関係性は外に行くほど薄く、中心に近づくほど濃く(強く)なることがわかる。
- 働きかけを実際に行う際には、中心である皆さんから近い人々に働きかけを行い、その方々がもう一歩、外側に位置する人々に働きかけることになる。
中心にいる人々だけでは働きかけや情報の伝達ができる範囲は限られているが、周囲にいる人々が一歩外へ働きかけることで、より多くの皆さんに知ってもらえるようになります。地方発の取り組みが全国的な取り組みになるのは、こうした場合です。 - 支援する層がどこに存在しているかが、明確になっていく。どの方向へアプローチしていくべきなのかが把握できるようになってくる。特にアプローチすべき新しい層の発見は、具体的な展開を進めやすくなる上、確実ならしめる。
参考 #23 ソーシャルセクターの支援者発見と組織状態の確認―ファンドレイジング・コンサルタントへの道
本稿で取り上げたい「ご質問」「ご相談」がございましたら、ぜひお聞かせください。


