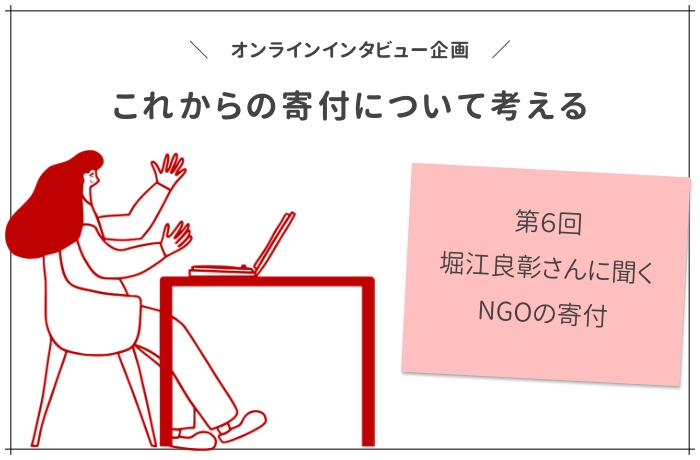インタビュー
ETIC調査「非営利団体のマネジメント人材育成」から見えたソーシャルセクターの課題と展望②
NPO法人エティック(以下、ETIC.)による調査「非営利団体のマネジメント人材育成」の担当者インタビュー、2回目です。
前回は、調査に至る山崎さんの想いやCHROの視点についての部分をお伝えいたしました。
前回の記事:ETIC調査「非営利団体のマネジメント人材育成」から見えたソーシャルセクターの課題と展望①
今回は、CHROの導入までは遠いと感じる小規模NPOへのヒントや、企業との連携、未来への展望についてのお話をお伝えいたします。
制度がなくても始められる人材育成
インタビュー③ 小規模NPOにとっての現実的なヒント
Q6. 5〜10人規模の団体でも、今日からできる“育成の第一歩”があるとすれば、どんなことから始めれば良いでしょうか?
育成の第一歩は「目指す成果に対する期待のすり合わせ」だと私たちは考えています。
具体的には、上司とメンバーが「目指す成果」や「現在の課題やギャップ」を言葉で共有し、一緒にどう成長していくかを話し合う時間を持つことです。これは制度がなくても、予算が限られていても実施可能な取り組みです。
実際、私たちが2024年に実施した、ソーシャルセクターマネージャー成長支援プログラム(![]() https://managers.etic.or.jp/)(17団体32名が参加)のカリキュラム内で、上司とメンバーの対話フォーマットを準備して必須課題として組み込んだところ、「最も効果的なコンテンツだった」との声が多く寄せられました。
https://managers.etic.or.jp/)(17団体32名が参加)のカリキュラム内で、上司とメンバーの対話フォーマットを準備して必須課題として組み込んだところ、「最も効果的なコンテンツだった」との声が多く寄せられました。
Q7. 「制度が整っていないから何もできない」という声には、どのように応えますか?
(山崎氏)今回の調査では、年間予算5,000万円以上の中規模NPOであっても、6割が採用専任の担当者を置かず、7割が育成担当者を設けていないという実態が明らかになりました。
私たちの所感では、例え規模の拡大に成功した名の知れた団体であったとしても、育成の制度が整っていることは非常にまれです。
だからこそ、今あるリソースの中で何を優先するかを考えることが重要です。そのプロセスとしては、状況を冷静に俯瞰し、どの打ち手から始めるべきかを経営者に伴走できる外部のパートナーを見つけることが、もっとも現実的で効果的な方法だと私たちは感じています。
Q8. 規模にかかわらず、育成が上手くいっているNPOや団体の事例があれば教えてください。
(山崎氏)育成が上手くいっている組織には、「人が育つことを心から喜べるリーダー」が多くいると感じます。
たとえば、業務の背景を丁寧に説明したり、振り返りの時間をしっかり確保したりと、日々の関わりの中で育成に時間をかけています。即戦力として期待される経験豊富なメンバーであっても、入社直後から一人立ちを求めるのではなく、その人が力を発揮できるような環境づくりに投資しているのです。
さらに、こうした「育つ風土」は、優秀な人材ほど転職先として重視します。つまり、育成への姿勢そのものが、団体の魅力や採用力にもつながっています。
Q9. 人と組織に向き合う中で、「これは忘れられないな」という場面や言葉があれば、印象的なものを教えてください。
(山崎氏)事業の多角化で人を採用しなければいけない、しかしなかなか採用ができない、というジレンマを抱えていたころに、アドバイザーから言われた言葉です。
「まずは、今いる人で何ができるかを考えるんだよ。」
難易度の高い課題に直面したり、リソースが逼迫していると、「どこかにスーパーマンはいないか」と外に求めてしまいがちです。 しかしこの言葉をきっかけに、今いる人たちが育つことを信じて向き合うことに気づかされました。そして、そうした組織文化が、結果的に優秀な人材を引き寄せる土台になる──非営利団体で働くマネージャーの一人として、後になって、その言葉の重みを実感しました。
「合意形成」がもたらす見えないリターン
お話の中の「育成の第一歩目」が、「目指す成果に対する期待のすり合わせ」という点は、私自身も全面的に同意でした。組織としてチームとして何を成そうとしているのかをすり合わせる、それは数値目標でも良いしスローガンでも良いし、ビジョンとしての方向性だけかもしれない。そこからギャップを表出化するだけでも、改善にはつながりそうです。これが一歩目だとすると、時間を捻出することでできそうです。
組織内の合意形成に関わるコミュニケーションを、「コミュニケーションコスト」として嫌う傾向があると聞くこともあります。しかし私は、組織内のコミュニケーションは投資だと考えており、メンバー同士の違いを認識しながら対話するスキルが高まれば、その分リターンとして成果も上がると考えています。この考え方は、今回の話にも通じるものだと感じました。
「人が育つことに喜びを感じるリーダーの存在」も重要です。成し遂げる事業の評価だけでなく、今一緒にいる「人」と共に何を成し遂げるかという視点を持つことが必要です。
ソーシャルセクターでは、人手が足りないからといってすぐに採用できるわけでもありません。今いるメンバーと、コミュニケーションを重ねて、より難易度が高い事業に取り組んでいくことが、育成の一歩目なのだと改めて気づかされました。
”共創的支援”が育てる人的資本
インタビュー④ 企業などとの外部支援体制について
Q10. 調査では「人材育成への資金が極端に少ない」ことも明らかになりました。企業など外部から、どのような形で関わってほしいと考えていますか?
(山崎氏)外部支援者のみなさまには、目に見える成果では測れないプロセスや組織基盤とも目を向け、一緒に育てていく仲間として関わっていただけたら嬉しいです。
調査レポートでも触れていますが、たとえば団体内の知見を言語化・体系化することや、メンバーのスキル向上、新しいネットワークの構築、外部の知恵を取り入れることなど──こうした“目に見えにくい資本”への投資が、団体の未来を支えると考えています。
中長期で成果を上げている団体ほど、人的資本や組織基盤への投資を重ねています。
Q11. 単なる助成金ではなく、“人材育成への共創的支援”という文脈では、どんな協力の形が理想だとお考えですか?
(山崎氏)ポイントは2つあります。
ひとつ目は、「資金の使い方に柔軟性を持たせること」。特にイノベーティブな取り組みに資金を提供する場合、計画通りにいかないことが当たり前です。そのとき、最も必要なところに迅速にリソースを投じられる柔軟性が、成果につながります。
ふたつ目は、「フラットな対話ができる関係性」。支援が思うように進まないときも、単に指摘するのではなく、「何が起きているのか」「次にどうするか」を率直に話し合える関係性ができていることが、結果的に現場と支援者双方のコミュニケーションコストを下げる基盤になります。
共創が、人材育成の地盤をつくる
本調査の特徴的な点は、人材育成において“外部支援者との共創”の可能性を探っているところにあります。
前半の質問でも「社会で解決する」という視点が示されていましたが、それを企業などの外部支援者に向けて、具体的な関わり方として示されていたのが印象的でした。なかでも「資金の使い方に柔軟性を持たせる」という提案は、現場でもよく耳にする課題であり、共創的支援を考えるうえで非常に本質的なポイントだと感じます。
また、「フラットな対話ができる関係性」への言及も、私としては特に重要だと感じました。これは単に“話しやすさ”ということではなく、現場の中にあるコミュニケーションコストを下げ、結果として相互理解と協働の質を高める基盤になると考えています。
人材育成の視点においても、こうした関係性づくりそのものが“投資”の対象になるのだと受け取りました。
“共に育つ”というマネジメント
インタビュー⑤ 未来へのメッセージ
Q12. 調査を通じて、非営利団体におけるマネジメントは、組織全体で担い合える視点や、いわゆる「管理職」「役職者」ではない多様な像があっても良いようにも見えてきました。組織を超えて学び合うことも必要そうです。このあたりのお考えをお聞かせください。
(山崎氏)「育成は、できる人ができない人を一方的に育てるものではなく、”共に育つ”もの」──これは、前述のプログラム設計をリードしてくださったコモンライト合同会社の宮崎さんの言葉でもあります。
あるプログラム受講者の上司は、メンバーの成長を通じて、自分自身の関わり方や組織文化を見直す必要に気づいたと話してくれました。育成とは、本人だけでなく、周囲にも変化をもたらすプロセスなのです。
また、経営者同士やマネージャー同士が事例を持ち寄るような、組織を超えた学びの場も今後ますます重要になると感じています。非営利の現場では、育成のベストプラクティスがまだ十分に共有されていないからこそ、「横のつながり」が鍵になると考えています。
Q13. 調査の中で、一番伝えたい箇所はどこになりますか。
(山崎氏)「非営利の現場にも、人的資本への投資が必要だ」ということです。
NPOの活動やサービスは、人の手によって生み出されています。その「人」が成長することが、組織の成長につながり、ひいては社会課題の解決に直結します。
だからこそ、活動の成果と組織づくりを切り離すのではなく、「人に投資すること」もまた社会的意義のある行為なのだと、伝えていきたいと思っています。
Q14. このレポートが、どんな人たちに届いてほしいですか?また、読んだ人が「これから自分も動こう」と思えるような一言を、お願いします。
(山崎氏)このレポートは、NPOの関係者だけでなく、企業・行政・メディアなど、多様な立場の方々にも読んでいただきたいです。
非営利の現場では、多くの実態がまだ知られておらず、誤解されていることもあります。だからこそ、「こんな課題があるのか」と知っていただくだけでも大きな第一歩です。
そして、もし何かが心に引っかかったなら──「自分にできることはなんだろう?」と、ぜひ一歩を踏み出すきっかけにしていただけたら嬉しいです。
“共に育つ”という投資
組織は結局、人の集まりです。そして、人が育つことこそが、組織の持続的な成長とインパクトの原点なのだと私も思います。
今回の調査やインタビューで語られていたのは、スキルや実績で人を評価し“引き上げる”ような育成ではなく、関わり合いの中で、互いの個性や背景を理解しながら育っていくプロセスの大切さでした。
こうした関係性の積み重ねそのものが、組織の文化になり、最終的には社会的な成果にもつながっていく──その視点を持てるかどうかが、これからのNPOにとって大事な問いなのかもしれません。
私自身伴走支援の立場として、単なる外部支援にとどまらず、組織とともに思考し、変化を生み出す“共に育つ関係”でありたいと思います。
そしてもう一つ、山崎さんの言葉を通じて強く残ったのが、「人に投資する」ということの本質です。予算や制度の限られた現場にこそ、あえて“人”にリソースを振り向けるという判断が、組織の価値観を映すのだとも感じます。
事業の成果と人の育ちは切り離せない。人との関わりそのものが、インパクトをつくる力になり得る。そのことを、私自身も改めて考えさせられました。
山崎さん、改めてありがとうございました。