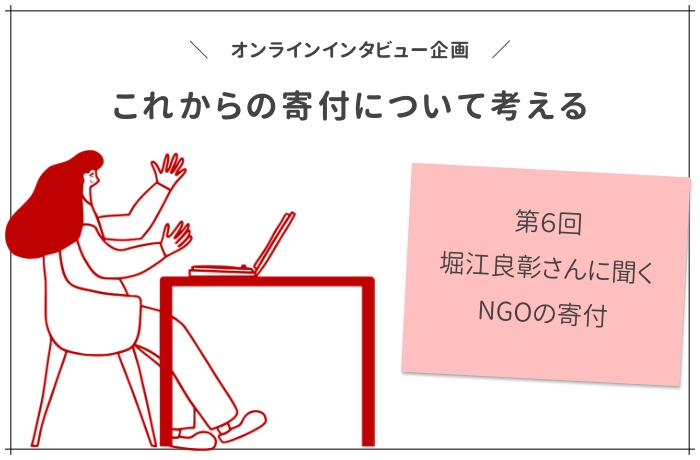インタビュー
ETIC調査「非営利団体のマネジメント人材育成」から見えたソーシャルセクターの課題と展望①
今年2025年2月に、NPO法人エティック(以下、ETIC.)からマネジメント人材の育成に関する実態調査の結果が発表されました。この業界では多くの人の関心テーマであり、その調査結果は肌感覚的にはこれまた多くの人が抱いていた通りで、報告書を興味を持って読んだ方も多いのではないでしょうか。
ETICプレスリリースはこちら:![]() https://etic.or.jp/news/2025/02/5634/
https://etic.or.jp/news/2025/02/5634/
マネジメント人材育成に関する調査から見えるもの
社会課題の最前線で活動する非営利団体が、持続的なインパクトを生み出し続けるためには、マネジメント人材の育成が不可欠です。ソーシャルセクターにかかわらず、どんな組織でもマネジメントについては考えて実施していく必要があり、活動を持続するにはその人材の育成が必要だと言えるでしょう。 にもかかわらずこの調査によれば、7割の団体が「育成に時間を割けない」、半数以上が「育成に使用できる資金が不足している」と回答しています。業界の実態を知る人ほど、こうした結果に“やはり”とうなずくのではないでしょうか。
まさにそれを、明確な形で示したのが今回の調査だと私は感じています。多くの人が感覚的に抱いていた課題を、数字で可視化した意義は大きいと感じました。
アンケート調査を行っていた段階から、調査担当者の方とお話をする機会があり、私自身も一部ご協力させていただいていました。 その経緯もあり、今回あらためてこの調査に込めた想いや、そこから見えてくる今後の展望、いま私たちが取り組めることについて、詳しくお話を伺いました。
インタビュー記事として、2回に分けてお届けいたします。

インタビュー日:2025年5月30日(役職はインタビュー実施時の肩書となります)
NPO法人ETIC.ソーシャルセクターマネージャー成長支援プログラム運営責任者:山崎 光彦氏
NPOの現場から見えた“育てにくさ”の構造
インタビュー①調査の背景とご自身の問題意識
Q1. 今回の調査を企画された背景や、特に問題意識を強く持っていた点を教えてください。
(山崎 光彦氏、以下、山崎氏)「人が育たないことが、事業成長のボトルネックになっている」──これは、私たちが多くのNPOと関わる中でよく聞かれてきた声です。とくに中間管理職やマネジメント層の育成は、多くの団体に共通する課題です。
その背景には、非営利団ならではの構造的な難しさがあるのではないか?という仮説が、今回の調査の出発点でした。また、この課題は団体の外からは見えにくく、十分に知られていないという問題意識もありました。だからこそ、まずは現場のリアルな声を集め、共に理解を深めることから始めたいと考えました。
この調査では、日本全国の非営利団体で経営や人材育成に携わる144名の方にご協力いただきました。データと現場の声をもとに、課題の全体像を捉え、必要な打ち手や支援を考える材料を提供する──それがこのレポートの目的です。
Q2. 現場で多くのNPOに接する中で、「人と組織」に関する変化や危機感を感じる場面はありますか?
(山崎氏)外部から採用されたマネジメント人材が、NPO特有の文化や仕事の進め方に馴染めず、早期に離職してしまう──こうしたケースは珍しくありません。
問題なのは、それを「本人の能力不足」や「団体の未熟さ」などと片付けられてしまいがちな点です。私たちは、そこに非営利セクター特有の「人が育ちにくい構造」があると考えています。
だからこそ、「どうすればNPOが人を育てられる組織になれるのか?」を、個別の団体の努力だけでなく、社会全体で考えていく必要があると感じています。
Q3. ご自身は「組織の中で成長した」と感じる経験がありますか?誰に、どんなふうに関わってもらったと感じますか?
(山崎氏)以前、私がベンチャーで新任マネージャーをしていたとき、他団体で長年マネジメント経験を積んだ方がサポートに入ってくださいました。
その方との対話の中で、チームの状況を客観的に見る視点を得たり、自分の立場を冷静に捉えるヒントをもらったりと、多くの学びがありました。同じ状況でも、経験者の視点はこれほど違うのかと驚かされました。
何より、その方の判断や行動の仕方が、マネージャーとしてのロールモデルになったのです。育成には時間も工数もかかりますが、ロールモデルの存在が人を育てる力になることを、改めて実感しました。
育成とは、“人と人の関係性”を育てること
最初に、そもそも山崎さんがなぜこの調査を企画したのか、その背景をお伺いしました。ETIC.で様々な団体と接していたからこそ、人材育成の課題を構造的に捉えていました。
話を伺いながら、「どうすればNPOが人を育てられる組織になれるのか?」という問いに対して、「社会全体で考えていく」というステップは、私には正直遠く感じてしまいました。
ただ、山崎さんのご経験からは、まずは身近な人との関係性の中で、学び合える環境をつくることが出発点なのだと受け取りました。
それは組織内でのロールモデルの存在かもしれませんし、外部のネットワークの中で刺激を受けるような関わりかもしれません。
育成という営みは、仕組みや制度だけではなく、人と人との関係性の中から立ち上がるものだとあらためて感じました。
育成にも戦略がいる―「経営目線」が問われる現場
インタビュー② 人材育成の課題と「CHRO」
Q4. 調査では「育成に手が回らない」「人材投資ができていない」などの課題が浮かびましたが、どのような構造的原因があるとお考えですか?
(山崎氏)非営利セクターにおける人材育成の困難さには、「人材」「ナレッジ」「資金」という3つの基盤の不足が背景にあると考えています。調査結果以外の実感も交えてお伝えしますね。
まず、人材について。非営利セクターには、人材育成の経験や専門性を持つ人の絶対数がそもそも少ないです。組織内にも、組織外にも、ロールモデルを見つけられないために、新任マネージャーが孤独に試行錯誤しているケースをよく見かけます。
次にナレッジ。世の中にはマネジメントに関する書籍や研修が豊富にありますが、非営利の現場に適した教材や知見は限られています。理想と現実のギャップに悩んでも、参照できる情報が乏しいのです。
そして資金。多くの支援者や資金提供者は、目に見える社会課題やサービス提供には投資しますが、「人」や「組織の基盤」には資金が届きにくいのが実情です。今回の調査でも、この点に関する切実な声が数多く寄せられました。 言い換えると、ビジネスの世界にあるような「支援のエコシステム」が、非営利の現場にはまだ十分に整っていない──それが、構造的課題の根底にあると考えています。
Q5. 調査レポートでは、「CHRO的能力を持った人材が求められる」という考察がありました。NPOが持続的に活動するためには、どのような「CHRO的視点」が必要になると思いますか?
(山崎氏)CHRO(Chief Human Resource Officer)とは、単なる人事の専門家ではなく、“経営の目線”で人材戦略を設計する役割だと理解しています。
NPOのように限られたリソースで活動する組織では、組織の文化や成長段階、事業の特性を深く理解したうえで、「いま、どこに力を注ぐべきか」という優先順位を冷静に見極める力、CHRO的視点はとても重要です。
しかし、こうした役割を担える人材は、現場ではまだ少ないのが現状です。そのため、非営利の経営に関心をもった外部からのプロフェッショナルサポートの重要性は、今後ますます高まっていくと感じています。
育成を“目の前の指導”から“組織の成長”へ引き上げる
山崎さんのお話からは、「人を育てる」という営みを、より広い視野で捉え直す必要性が伝わってきました。 「育成」という言葉が示すものを、日々のマネジメントから、組織全体の戦略へとスライドさせて捉えていく——そんな視座の転換が、求められているのかもしれません。
お話に出てきた「CHRO」という視点の重要性は、非常によく理解できます。一方で、リソースが限られるNPOがその役割まで担えるかというと、正直なところ現実的には難しい部分もあるのではないかと感じました。だからこそ、「支援のエコシステム」を社会全体で育てていく意識が、今後ますます重要になってくると考えています。
私自身も、知識やノウハウを伝えるだけではなく、それを実行する“人”をどう育てるのか、またその人のモチベーションと組織の目的をどうすり合わせていくのか、という点に関心を持ち続けています。
育成を一人の課題ではなく、組織の構造として捉えること、そして経営の視点から向き合っていくことが、あらためて重要だと感じました。
次回の記事では、「CHRO」という視点に至るにはまだ距離がある小規模な団体にとって、現実的に取り得るヒントや、企業など外部の力をどう活用できるかといった点について、ご紹介していきます。